|
|
| |
目
次 |
|
01外観
Ⅰプロローグ縄文その世界
世界に誇る縄文土器の造形美にせまる
Ⅰ-(1)火焔土器
Ⅰ-(2)注口土器
Ⅰ-(3)様々な形の土器
Ⅱ 土器が語る時代の変化
Ⅱ-(1) 縄文の誕生(草創期)
Ⅱ-(2) 文様の確立(早期・前期)
Ⅱ-(2)01縄文時代 早期
Ⅱ-(2)02縄文時代 前期土器
Ⅱ-(3) 進化と多様(中期・後期)
Ⅱ-(3)01縄文時代 中期土器
Ⅱ-(3)02縄文時代 後期土器
Ⅱ-(4) 縄目使用の衰退
(後期末~晩期前半)
|
Ⅲ祈りの道具と装身具
Ⅲ-(1)01土偶
Ⅲ-(1)02土偶
Ⅲ-(2)01土面
Ⅲ-(3)石棒
Ⅲ-(4)装身具
Ⅲ-(5)縄文晩期墓地群の発見
Ⅳ交流の証
Ⅳ-(1)列島各地の影響を受けた土器
Ⅳ-(1)01水銀朱・サヌカイト
Ⅳ-(1)02列島各地の影響を受けた土器
Ⅳ-(2)02列島各地の石材で製作された石器
Ⅳ-(2)05後期・晩期の土器
Ⅳ-(3)特殊な文様の土器 |
Ⅴエピローグ
縄文の食料と米作り、そして弥生へ
Ⅴ-(2)弥生の水田稲作
Ⅵ年表・遺跡地図等
Ⅵ-(2)兵庫県縄文時代主要遺構年表
|
|
| |
01外観
|
| |
Ⅰ プロローグ縄文その世界
世界に誇る縄文土器の造形美にせまる
|
狩猟採集を糧としていた縄文時代。人々は自然に生かされ生活していました。縄文人は自然の恵みである食料を煮炊きする土器に特別な思いを込め、各地方独自の造形や装飾性に富んだ文様や繊細な縄目文様を施した素焼きの器を製作したのです。 |
 |
 |
縄文土器部位名称 |
 |
火焔土器文様展開写真
諏訪前遺跡
新潟県津南町 |
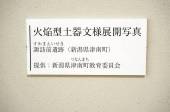 |
 |
|
|
|
|
|
|
| |
| |
Ⅰ-(1) 火焔土器 深鉢 諏訪前遺跡 縄文中期 津南町
|
火焔土器は燃えさかる炎が天に向かって広がる造形を持つ深鉢形土器で、口縁部一面にあしらわれた鋸歯状のフリルや鶏頭冠把手に付属するハート形の窓やトンボの眼鏡ような突起が正確に配置されている秀逸品です。火焔型土器は新潟県を中心に約5千年前の縄文時代中期に作られたものです。芸術家岡本太郎がその芸術性に気付化された土器の一つで縄文芸術を代表するものです。 |
 kaen-doki/DSC02965_thumb.jpg) |
(1) 火焔土器 kaen-doki/DSC02965a_thumb.jpg) |
鶏形把手 kaen-doki/DSC02965b_thumb.jpg) |
 kaen-doki/DSC02967_thumb.jpg) |
 kaen-doki/DSC02968_thumb.jpg) |
深鉢形土器
火焔型土器
諏訪前遺跡 縄文中期
新潟県津南町
 kaen-doki/DSC02969_thumb.jpg) |
 kaen-doki/DSC02970_thumb.jpg) |
 kaen-doki/DSC02971_thumb.jpg) |
 kaen-doki/DSC02972_thumb.jpg) |
 kaen-doki/DSC02974_thumb.jpg) |
 kaen-doki/DSC02975_thumb.jpg) |
 kaen-doki/DSC02976_thumb.jpg) |
|
| |
Ⅰ-(2) 注口土器 椎塚貝塚 縄文後期 加曽利B1式 茨城県稲敷市
|
注ぎ口を付けた液体を入れる容器で、器形はまるで現代の土瓶を思わせる注口土器です。文様は「S字状文」から放たれた細かなヘラ書きの線が装飾性豊かな幾何学文様となり、器面を覆っています。関東地方後期前半の注口土器では一対の把手をつくり蔓などで吊り下げたと考えられますが、この例は蔓までも土器と一体で作られている点が珍しいものです。縄文土器として国指定重要文化財第1号で、高校の日本史副読本にも掲載されました。 |
 cyukou-doki/000DSC02978_thumb.jpg) |
 cyukou-doki/00DSC03033_thumb.jpg) |
 cyukou-doki/DSC02979_thumb.jpg) |
注口土器 cyukou-doki/DSC02979a_thumb.jpg) |
S字状文
辰子馬考古資料館 cyukou-doki/DSC02979b_thumb.jpg) |
注口土器 椎塚貝塚 縄文後期 加曽利B1式 cyukou-doki/DSC02980_thumb.jpg) |
注口土器 椎塚貝塚
茨城県稲敷市 cyukou-doki/DSC02980a_thumb.jpg)
縄文後期 加曽利B1式 |
 cyukou-doki/DSC02981_thumb.jpg) |
 cyukou-doki/DSC02982_thumb.jpg) |
 cyukou-doki/DSC02983_thumb.jpg) |
 cyukou-doki/DSC02984_thumb.jpg) |
 cyukou-doki/DSC02985_thumb.jpg) |
 cyukou-doki/DSC02986_thumb.jpg) |
 cyukou-doki/DSC02987_thumb.jpg) |
 cyukou-doki/DSC02988_thumb.jpg) |
 cyukou-doki/DSC02989_thumb.jpg) |
 cyukou-doki/DSC02990_thumb.jpg) |
|
|
| |
Ⅰ-(3) 様々な形の土器 淡路市佃遺跡 縄文後期
|
西日本最大級の縄文遺跡である兵庫県淡路市佃遺跡からは多量の遺物が出土しました。その内、130点余りの後期の土器を完成品に復元しました。各器種や大きさの違う土器の数々をピラミッド状に配置しました。これら兵庫の縄文時代を代表する土器から縄文人の造形感覚を感じて下さい。 |
※淡路市佃遺跡は、兵庫県立考古博物館設立の基盤となった遺跡で、この遺跡の出土品を中心に展示が構成されているほど重要な遺跡です。
|
Ⅰ-(3)01注口土器 兵庫県淡路市佃遺跡 縄文時代後期 約3500年前
|
Ⅰ-(3)02佃遺跡の土器
深鉢形土器
|
Ⅰ-(3)03注口土器
|
Ⅰ-(3)04浅鉢形土器
|
Ⅰ-(3)05深鉢形土器
|
Ⅰ-(3)06深鉢形土器
|
Ⅰ-(3)07注口土器
07/000DSC03111_thumb.jpg) |
07/00DSC03089_thumb_1.jpg) |
07/DSC03087_thumb_1.jpg) |
07/DSC03088_thumb_1.jpg) |
07/DSC03090_thumb_1.jpg) |
07/DSC03091_thumb_1.jpg) |
注口土器07/DSC03092_thumb_1.jpg)
佃遺跡 淡路市
縄文後期 |
注口土器07/DSC03093_thumb_1.jpg)
佃遺跡 淡路市
縄文後期 |
07/DSC03094_thumb_1.jpg) |
|
|
|
|
Ⅰ-(3)08浅鉢形土器
|
Ⅰ-(3)09壺形土器
|
| |
| |
| |
| |
Ⅱ 土器が語る時代の変化
|
旧石器時代では寒冷な気候が続きましたが、約1万4千年前から徐々に温暖化に転じました。その結果、海面が上昇し、それまで針葉樹が主体であった森林には常緑樹や落葉広葉樹が繁茂し、食料の変化をもたらしました。陸地でシカ。・イノシシをはじめとする小動物やドングリなどの木の実が採れ、海産物も多くなりました。これらの食料を煮炊きするために土器が作られ、縄文時代をむかえます。
縄文時代は「定住・土器の使用・弓矢を用いた狩猟・海への進出」など人々の生活も大きく変化しました。中でも土器は食料の煮炊きに欠かせない調理用具であると共に、形態や製作技法、施された文様には時代の変化ゃ地域の特色が如実に表れており、時代を表す1万年分の"物差し"として考古学で特に重要な存在です。 |
|
Ⅱ-(1) 縄文の誕生(草創期)
|
草創期の縄文土器は文様のない「無文土器」から始まります。その後。粘土紐による「隆起線文土器」、全体を爪などで文様を付けた「爪形文土器」、
縄で文様を描く「多縄文土器」の順に移り変わります。
豊岡市神鍋遺跡や但馬高原に位置する遺跡では、爪形文土器が採集され、豊岡市伊府遺跡では微細な土器片が、淡路市まるやま遺跡でも土器の小片が出土しています。これらから、県内にも同時代の遺跡が僅かながら存在します。
縄文時代草創期は土器を使い始めた時期ですが、石器の作りは規則的に原石を割り、丁寧に仕上げています。これまで発掘調査によって明らかになった跡群は伊府遺跡(豊岡市)、国領遺跡(丹波市)、藤岡山遺跡(篠山市)、まるやま遺跡(淡路市)があります。 |
 Jomon-tanjo/00DSC03035_thumb.jpg) |
 Jomon-tanjo/DSC02769_thumb.jpg) |
土器が語る時代の変化 Jomon-tanjo/DSC02770_thumb.jpg) |
縄文の誕生 (草創期)
 Jomon-tanjo/DSC02771_thumb.jpg) |
 Jomon-tanjo/DSC02771a_thumb.jpg)
爪形文(津南町)
尖頭器(藤岡山遺跡)
篠山市 |
 Jomon-tanjo/DSC02772_thumb.jpg)
縄文の夜明け
釜口船頭ヶ内遺跡
淡路市 |
 Jomon-tanjo/DSC02773_thumb.jpg) |
石器(尖頭器ほか)
藤岡山遺跡(篠山市)
 Jomon-tanjo/DSC02774_thumb.jpg)
旧石器末~
縄文草創期 |
石器(有茎尖頭器)
国領遺跡(丹波市) Jomon-tanjo/DSC02775_thumb.jpg)
縄文草創期 |
石器(木葉形尖頭器他)・土器
まるやま遺跡(淡路市) Jomon-tanjo/DSC02776_thumb.jpg)
縄文草創期ほか |
 Jomon-tanjo/DSC02777_thumb.jpg) |
 Jomon-tanjo/DSC02778a_thumb.jpg) |
石器(局部磨製石斧他) Jomon-tanjo/DSC02781_thumb.jpg)
伊府遺跡(豊岡市)
縄文草創期 |
 Jomon-tanjo/DSC02782a_thumb.jpg) |
 Jomon-tanjo/DSC02783a_thumb.jpg) |
深鉢形土器
爪形文+押圧縄文土器 Jomon-tanjo/DSC02785_thumb.jpg)
卯ノ木南遺跡 津南町
縄文草創期 |
 Jomon-tanjo/DSC02787_thumb.jpg) |
|
|
Ⅱ-(2) 文様の確立(早期・前期)
|
縄文時代早期になると西日本を中心に底が尖った押型文土器が作られます。山形や楕円形の模様を刻んだ型の棒を転がして土器の内外に施文されています。また、押型文土器は時代の経過に伴い変化します。
前期には底が平らに変化し、縄を用いて描かれた文様は規則的なものからより複雑なものへと変わります。また、土器の厚さは薄くなり、煮炊きする上で効率的なものへ変化します。 |
|
Ⅱ-(2)01縄文時代 早期
 01/000DSC03036_thumb.jpg) |
 01/00DSC02769a_thumb.jpg) |
 01/00DSC02797_thumb.jpg) |
文様の確立 01/DSC02789_thumb.jpg) |
 01/DSC02789a_thumb.jpg)
神鍋遺跡(豊岡市)
深鉢 縄文文様
山宮遺跡(豊岡市)
押形文(上)楕円文(下) |
 01/DSC02790_thumb.jpg) |
深鉢形土器 01/DSC02791_thumb.jpg)
山宮遺跡(豊岡市)
縄文早期
高山寺式
(ポジティブ楕円文) |
 01/DSC02792_thumb.jpg) |
 01/DSC02793_thumb.jpg) |
|
|
|
縄文時代 早期土器
石器
(尖頭器・ナイフ形石器・磨石) 01/DSC02794_thumb.jpg)
山宮遺跡(豊岡市)
縄文早期 |
深鉢形土器 01/DSC02796_thumb.jpg)
山宮遺跡(豊岡市)
縄文早期
黄島式(山形文) |
深鉢形土器 01/DSC02798_thumb.jpg)
福本遺跡(神河町)
縄文早期 福本式 |
深鉢形土器 01/DSC02800a_thumb.jpg)
福本遺跡(神河町)
縄文早期 福本式 |
縄文の暮らし
神河町 01/DSC02802_thumb.jpg) |
深鉢形土器(無文土器) 01/DSC02803_thumb.jpg)
福本遺跡(神河町)
縄文早期 |
深鉢形土器 01/DSC02805_thumb.jpg)
都賀遺跡(神戸市)
縄文早期 高山寺式 |
 01/DSC02806_thumb.jpg) |
|
|
|
Ⅱ-(2)02縄文時代 前期土器
|
| |
Ⅱ-(3) 進化と多様(中期・後期)
|
縄文時代中期の西日本では遺跡数は増加するものの、東日本の極端な遺跡増加には及びません。
土器の造形は東日本の北信越地方の火焔型土器や中部地方の勝坂式土器、関東地方の加曾利E式のような大胆な造形に比べて、西日本では文様の縄目が大きくなることに加え複雑化する程度の変化が見られる程度です。
中期末には深鉢形土器の口縁部が拡張・肥厚・突起が見られるものもあります。(丁・柳ケ瀬遺跡例)
後期には土器の種類が深鉢に加え、浅鉢・注口・台付鉢(高坏)などが出現し多様化します。深鉢形土器の口縁部は徐々に平らなものへと変化します。文様は縄文を施した上に曲線や直線の沈線を描き、その後に縄文の一部を磨り消す「磨消縄文」文様を描き出します。 |
|
Ⅱ-(3)01縄文時代 中期土器
01/00DSC02827_thumb.jpg) |
進化と多様
(中期・後期)
01/01DSC02819a_thumb.jpg) |
01/01DSC02819b_thumb.jpg)
藤岡山遺跡(篠山市)
丁・柳ヶ瀬遺跡(姫路市)
深鉢口縁部の突起 |
01/01DSC02826_thumb.jpg) |
深鉢形土器01/DSC02820_thumb.jpg)
神子曽遺跡(南あわじ市)
縄文中期 船元Ⅲ式 |
01/DSC02821_thumb.jpg) |
01/DSC02823_thumb.jpg) |
深鉢形土器01/DSC02829_thumb.jpg)
本山遺跡(神戸市)
縄文中期 船元Ⅳ式 |
01/DSC02831_thumb.jpg) |
深鉢形土器01/DSC02834a_thumb.jpg)
平方遺跡(太子町)
縄文中期 里木Ⅱ式 |
鉢形式土器01/DSC02837_thumb.jpg)
平方遺跡(太子町)
縄文中期 船元Ⅳ式 |
|
|
Ⅱ-(3)02縄文時代 後期土器
02/DSC02832_thumb.jpg) |
佃ムラの様子02/DSC02833_thumb.jpg) |
02/DSC02835_thumb.jpg) |
深鉢形土器02/DSC02839_thumb.jpg) |
02/DSC02841_thumb.jpg)
丁・柳ヶ瀬遺跡(姫路市)
縄文中期 北白川C式 |
鉢形土器02/DSC02842_thumb.jpg)
姫路市内出土
縄文後期 中津式 |
02/DSC02843_thumb.jpg) |
鉢形土器02/DSC02846_thumb.jpg)
藤岡山遺跡(篠山市)
縄文後期 福田KⅡ式 |
深鉢形土器(無文土器)
02/DSC02848_thumb.jpg)
平方遺跡(太子町)
縄文後期 |
02/DSC02849_thumb.jpg) |
深鉢形土器02/DSC02853_thumb.jpg) 東南遺跡(太子町) 東南遺跡(太子町)
縄文後期
北白川上層式 |
02/DSC02857_thumb.jpg) |
深鉢形土器02/DSC02857DSC02851_thumb.jpg)
東南遺跡(太子町)
縄文後期
北白川上層式 |
深鉢形土器02/DSC02858_thumb.jpg)
丁・柳瀬遺跡(姫路市)
縄文中期 北白川C式 |
深鉢形土器02/DSC02860_thumb.jpg)
平方遺跡(太子町)
縄文後期 中津式 |
深鉢形土器02/DSC02861_thumb.jpg)
今宿丁田遺跡(姫路)
縄文後期 中津式 |
深鉢形土器02/DSC02863_thumb.jpg)
原野・沢遺跡(神戸市)
縄文後期 四ッ池式 |
深鉢形土器02/DSC02865_thumb.jpg)
東南遺跡(太子町)
縄文後期 北白川上層式 |
02/DSC03037_thumb.jpg) |
|
|
|
|
|
|
Ⅱ-(4) 縄目使用の衰退(後期末~晩期前半) 縄文時代晩期の土器
|
縄文時代草創期から土器の文様として縄目の文様「縄文」が付けられました。東日本では縄文時代の全期間を通じて縄文が使われ、その後弥生時代まで縄文が付けられました。
しかし、西日本ではこの縄文は後期後葉から次第に使われなくなりります。その変化は淡路市佃遺跡の土器文様が縄文から貝殻外面の凸凹を押し当てた「擬縄文」、そして巻貝外面の凸部を押引きした「凹線」へと変化し、晩期には「沈線」や文様がない土器「無文」となります。
兵庫県を含む近畿地方の晩期前葉から中葉には縄文土器に特徴的な文様はほとんど使われなくなりました。
縄目文様が使われなくなった原因が生活や社会の変化によるものか研究が続けられていますが、まだ、はっきりわかっていません。 |
 jomon-suitai/DSC02867_thumb.jpg) |
縄目使用の衰退 jomon-suitai/DSC02868_thumb.jpg) |
縄目模様から凹線文へ jomon-suitai/DSC02869_thumb.jpg) |
縄目模様から凹線文へ jomon-suitai/DSC02871_thumb.jpg) |
浅鉢形土器 jomon-suitai/DSC02872a_thumb.jpg)
篠原遺跡(神戸市)
縄文晩期 篠原式 |
鉢形土器 jomon-suitai/DSC02873a_thumb.jpg)
篠原遺跡(神戸市)
縄文晩期 篠原式 |
深鉢形土器 jomon-suitai/DSC02874_thumb.jpg)
篠原遺跡(神戸市)
縄文晩期 篠原式 |
 jomon-suitai/DSC02875_thumb.jpg) |
 jomon-suitai/DSC02876_thumb.jpg) |
 jomon-suitai/DSC02877_thumb.jpg) |
深鉢形土器 jomon-suitai/DSC02878_thumb.jpg)
篠原遺跡(神戸市)
縄文晩期 篠原式 |
 jomon-suitai/DSC02879_thumb.jpg) |
 jomon-suitai/DSC02880_thumb.jpg) |
 jomon-suitai/DSC02881_thumb.jpg) |
|
|
|
|
|
| |
| |
Ⅲ祈りの道具と装身具
|
縄文人は畏敬の念や願いを込め祈りの道具を作り、マツリや日常生活において身体を飾る装身具を身に着けました。
土偶は生命誕生などのマツリに、人の形をした「土偶」や男根を模した「石棒」などは個人・家族のマツリに、顔を模した「土面」、石棒のうち刀や剣の形をした「石剣石刀類」などは集団のマツリに使われたのかもしれません。
アクセサリーとして、玦状耳飾・耳栓といったイヤリング、勾玉・垂飾などの首飾りも少ないながら見つかっています。
縄文時代の人々が思いを込めて作り、マツリに使用した道具の数々を紹介します。 |
|
Ⅲ-(1)01土偶
|
自然と共に生きた縄文時代のでは草創期期から土偶が造られ、マツリが行われていました。多くは女性を表現した粘土の素焼き像です。
山梨県釈迦堂遺跡群では1千個体以上の土偶が出土しました。
兵庫県では前・後・晩期の土偶20個体が発見されています。後・晩期に大型化しますが、その中でも淡路市佃遺跡では復元全長27cmとなる西日本でも最大級の土偶が出土しました。また、雪眼鏡の遮光器のように見える遮光器土偶が神戸市篠原遺跡から出土しました。
青森県亀ヶ岡遺跡など東北地方を中心に出土する土偶の西端の出土例です。 |
01dogu/00DSC03038_thumb.jpg) |
祈りの道具と装身具01dogu/DSC02992_thumb.jpg) |
01dogu/DSC02994_thumb.jpg) |
画像参考資料
遮光器土偶01dogu/DSC02994a_thumb.jpg) |
亀ヶ岡遺跡
(青森県津軽市)
縄文時代晩期 |
|
01dogu/DSC02994c_thumb.jpg) |
遮光器土偶01dogu/DSC02996_thumb.jpg) |
亀ヶ岡遺跡
(青森県津軽市)
縄文時代晩期 |
遮光器土偶
01dogu/DSC02997_thumb.jpg) |
篠原遺跡 (神戸市)
縄文晩期 |
土偶01dogu/DSC02999_thumb.jpg) |
|
Ⅲ-(1)02土偶
02dogu/00DSC03024_thumb.jpg) |
02dogu/00DSC03026_thumb.jpg) |
土偶02dogu/00DSC03026a_thumb.jpg)
雲井遺跡(神戸市)晩期
生田遺跡(神戸市)後期 |
土偶 縄文晩期02dogu/00DSC03026b_thumb.jpg)
口酒井遺跡(伊丹市)
宇治川南遺跡(神戸市)
佃遺跡(淡路市) |
土偶 晩期02dogu/DSC03025_thumb.jpg)
佃遺跡(淡路市) |
土偶 後期
02dogu/DSC03025a_thumb.jpg)
東南遺跡(太子町) |
|
Ⅲ-(2)01土面
|
目・眉・鼻・口などの顔面を表現した土製の仮面が「土面」です。
縄文時代後期初頭に出現しました。全国の出土例は僅か150例ほどで、近畿地方では大阪府と滋賀県、兵庫県で10例があります。
目の両側に孔が穿たれたものは紐を通し、顔面や頭部に装着した仮面と考えられます。同じ土製品の土偶と比べてその発生は遅れることから、異なったマツリに使われたと考えられます。 |
domen/00DSC03006_thumb.jpg) |
土面domen/00DSC03007_thumb.jpg) |
土面domen/DSC03002_thumb.jpg) |
domen/DSC03003_thumb.jpg)
大原出土:岩手県一関市
縄文晩期 |
土面
domen/DSC03004_thumb.jpg)
富島遺跡(淡路市)後期 |
domen/DSC03004a_thumb.jpg) |
|
Ⅲ-(3)石棒
|
長い棒状の磨製石器である石棒は男根状のものがよく知られていますが、円棒のままで無頭の石棒もあります。
石棒は断面形により円形「石棒型」、両刃の「石剣型」、片刃の「石刀形」があり、刃を持つものは石剣石刀類と呼ばれています。
大型の石棒は実用的ではないことから、大地に設置され集落での大規模なマツリに使われ、小型の石棒や石剣石刀類は手にかざして儀式に使われたと考えられます。 |
ishibo/DSC03016a_thumb.jpg) |
石棒ishibo/DSC03017_thumb.jpg) |
石棒・石棒未成品ishibo/DSC03019DSC03016ab_thumb.jpg)
見蔵岡遺跡(豊岡市)
縄文後期 |
ishibo/DSC03020_thumb.jpg) |
ishibo/DSC03021_thumb.jpg) |
ishibo/DSC03022_thumb.jpg)
堂田遺跡(姫路市)晩期
梶遺跡(丹波市)後期 |
|
Ⅲ-(4)装身具
|
縄文時代の装身具には、耳飾り(イヤリング)や垂飾・勾玉(ペンダント)などがあります。石製耳飾りには中国の玦に似た「玦状耳飾」や土製の耳栓もあります。これらの耳飾りは耳たぶに孔を開けて装着したと考えられています。ペンダントにはヒスイなどの石製品が見られます。これらの装飾品から現代人と似る「オシャレな縄文人」が想像できます。 |
土製・石製装身具
|
| |
Ⅲ-(5)縄文晩期墓地群の発見
 banki-bochigun/00DSC02882_thumb.jpg) |
 banki-bochigun/00DSC02883_thumb.jpg)
埋葬用土器 |
 banki-bochigun/00DSC02884_thumb.jpg)
晩期墓地群の発見
佃遺跡(淡路市) |
深鉢形土器 banki-bochigun/00DSC02888_thumb.jpg) |
 banki-bochigun/00DSC02892a_thumb.jpg)
坂本遺跡(加古川市)
縄文晩期 |
|
深鉢形土器 banki-bochigun/01DSC02890_thumb.jpg) |
 banki-bochigun/02DSC02889_thumb.jpg)
坂本遺跡(加古川市)
縄文晩期 |
 banki-bochigun/03DSC02887_thumb.jpg)
二次葬用土器 |
 banki-bochigun/03DSC02894_thumb.jpg) |
 banki-bochigun/DSC02886_thumb.jpg) |
 banki-bochigun/DSC02890a_thumb.jpg) |
|
| |
| |
Ⅳ交流の証
|
ムラで使われた土器などの多くはムラの中やその周辺で作られたと考えられています。しかし、縄文土器の形・文様・胎土や石器の原材料を観察し産地同定すると、明らかにその地方以外の影響を受けたものがあります。その距離は数百km以上に及ぶものもあります。
縄文時代の物質や文化は交流を通じて伝搬したものですが、当時の海上や陸路を通じて影響を及ぼした貴重な遺物から交流を検証します。 |
|
Ⅳ-(1)列島各地の影響を受けた土器
|
交通網や通信手段など、現代とは全く違った縄文時代にどのような土器の文様などが伝わっていたのか見てみます。
交流の証として見られる土器には、東北地方から九州地方まで各地方の特徴を持つ土器があります。これらの多くは直接各地方から持ち込まれたというよりは、形や文様が長年にわたり伝わった物と考えられます。 |
|
Ⅳ-(1) 01
 01/00DSC03040a_thumb.jpg) |
 01/DSC02896_thumb.jpg) |
交流の証
 01/DSC02897_thumb.jpg) |
佃遺跡にみる各地との交流 01/DSC02898_thumb.jpg) |
水銀朱の精製に関係した土器や石器 01/DSC02898a_thumb.jpg) |
北陸系 01/DSC02898b_thumb.jpg) |
環頭・中部系 01/DSC02898c_thumb.jpg) |
東海系 01/DSC02898d_thumb.jpg) |
四国金山のサヌカイト 01/DSC02898e_thumb.jpg) |
九州系 01/DSC02898f_thumb.jpg) |
|
|
|
Ⅳ-(1) 01b
水銀朱の精製に関する石器や土器
水銀朱の精製に関する石器や土器 01b/DSC02898a_thumb.jpg) |
 01b/DSC02898aa_thumb.jpg)
石皿・敲石・土器 |
水銀朱を入れた土器 01b/DSC02898ab_thumb.jpg) |
水銀朱
 01b/DSC02898ac_thumb.jpg) |
水銀朱はもともと水銀と硫黄が化合した硫化水銀で、辰砂を原料とする。
色は朱色でベンガラ(酸化第二鉄)などと共に絵の具として利用され、彩色が鮮明で変色しにくい水銀朱は採取量が少なく貴重な素材であったことがうかがわれる。 |
四国金山のサヌカイト
四国金山のサヌカイト 01b/DSC02898e_thumb.jpg) |
サヌカイト 01b/DSC02898ea_thumb.jpg)
黒くて緻密な割れ口を持つ石。
この性質が石器として長らく日本各地で使われるようになった。 |
 01b/DSC02898eb_thumb.jpg)
香川県金山 |
 01b/DSC02898ec_thumb.jpg)
サヌカイトのデポ遺構 |
|
| |
Ⅳ-(1) 02
列島各地の影響を受けた土器
|
交通網や通信手段など、現代とは全く違った縄文時代にどのような土器の文様などが伝わっていたのか見てみます。
交流の証として見られる土器には、東北地方から九州地方まで各地方の特徴を持つ土器があります。これらの多くは直接各地方から持ち込まれたというよりは、形や文様が長年にわたり伝わった物と考えられます。 |
 02/00DSC03040a_thumb_1.jpg) |
関東・山陰・九州系土器 02/DSC02899a_thumb.jpg)
山宮遺跡(豊岡市)
縄文早期 |
 02/DSC02900_thumb.jpg)
鵜ヶ島台・茅山下層式
平栫式
宮ノ下・菱根式
長山式 |
 02/DSC02901a_thumb.jpg)
中津式両耳壷 |
 02/DSC02902_thumb.jpg)
上野スサキ遺跡
新潟県津南町
縄文後期 |
列島各地の影響を受けた土器 02/DSC02905_thumb.jpg) |
|
Ⅳ-(1) 03列島各地の影響を受けた土器
 03/DSC02904_thumb.jpg) |
関東・中部・東海・北陸・九州地域の土器 03/DSC02906aa_thumb.jpg) |
東海系 03/DSC02912_thumb.jpg) |
九州系 03/DSC02914_thumb.jpg) |
北陸系 03/DSC02915a_thumb.jpg) |
関東・中部系 03/DSC02916_thumb.jpg) |
|
Ⅳ-(1) 04
 04/DSC02907a_thumb.jpg) |
加曽利E式土器 04/DSC02910f_thumb.jpg) |
深鉢形土器 04/DSC02911_thumb.jpg)
丁・柳瀬遺跡(姫路市)
縄文中期 加曽利E式 |
|
Ⅳ-(1) 05
|
| |
| Ⅳ-(2) |
Ⅳ-(2)00土器
00pottery/000DSC03041_thumb.jpg) |
00pottery/000DSC03115_thumb.jpg) |
注口土器・鉢形土器00pottery/000DSC03116_thumb.jpg) |
注口土器00pottery/000DSC03117_thumb.jpg)
篠原遺跡(神戸市)晩期 |
鉢形土器00pottery/000DSC03118_thumb.jpg)
篠原遺跡(神戸市)晩期 |
00pottery/000DSC03135_thumb.jpg) |
孔列土器
丹塗り磨研八ツ手状黒斑土器
鉢形土器00pottery/DSC03123_thumb.jpg)
口酒井遺跡(伊丹市)
縄文晩期 |
00pottery/DSC03124_thumb.jpg) |
丹塗り磨研八ツ手状
黒斑土器00pottery/DSC03126_thumb.jpg) |
|
| |
Ⅳ-(2)02列島各地の石材で製作された石器
|
Ⅳ-(2)02-3結晶片岩
|
中央構造線以南の三波川変成帯を構成する岩石が結晶片岩です。結晶片岩には緑色片岩や紅簾片岩(こうれん)などがあります。
兵庫県では淡路島の南4kmに位置する沼島で産出し、島全体が結晶片岩で構成されています。この他、徳島県吉野川以南や和歌山県の紀ノ川以南の広範囲に産出します。
結晶片岩は縄文時代以降の各時代に流通し、現代でも庭石などに使用されています。 |
02-3kessyo-hengan/00DSC03129_thumb.jpg) |
石棒
結晶片岩製石棒02-3kessyo-hengan/DSC03127_thumb.jpg)
丁・柳瀬遺跡
(姫路市)晩期 |
02-3kessyo-hengan/DSC03127a_thumb.jpg) |
02-3kessyo-hengan/DSC03127ab_thumb.jpg) |
結晶片岩02-3kessyo-hengan/DSC03128_thumb.jpg) |
|
Ⅳ-(2)02-4サヌカイト
|
紀伊半島中部から九州北部に分布する安山岩の一種。旧石器時代から弥生時代まで石器の材料として使われました。
遺跡から出土する打製石器の多くはサヌカイトです。成分分析の結果、香川県金山産、兵庫県岩屋産、大阪府と奈良県境の二上山産が見られます。
これらを淡路市佃遺跡出土石鏃の分析結果と各産地周辺で採集した原石とを比較しました。これらは長期間にわたり産地からの供給ルートがあることから、絶えず交流していたことが分かります。
※比較してどうだったかの結論が欠如している。ケツなしの結文でした。 |
02-4sanukaito/00DSC03143_thumb.jpg) |
サヌカイト02-4sanukaito/00DSC03144a_thumb.jpg) |
サヌカイト製石鏃02-4sanukaito/00DSC03147_thumb.jpg)
左:金山産
中:岩屋産
右:二上山 |
02-4sanukaito/DSC03146_thumb.jpg)
佃遺跡(淡路市)
縄文後期 |
02-4sanukaito/DSC03189_thumb.jpg) |
02-4sanukaito/DSC03190_thumb.jpg) |
02-4sanukaito/DSC03191a_thumb.jpg) |
|
|
|
|
|
|
Ⅳ-(2)02-5黒曜石
|
黒曜石は火成岩の一種でガラス質の割れ口は光沢を発します。産地は北海道白滝地方や長野県和田峠が有名です。
兵庫県内からは島根県隠岐産や大分県姫島産の石器や剥片が出土しています。日本海や瀬戸内海を渡ってもたらされました。 |
黒曜石02-5kokuyo-seki/DSC03148_thumb.jpg)
左:隠岐島産
右:姫島産
東南遺跡(太子町)後期 |
黒曜石02-5kokuyo-seki/DSC03148a_thumb.jpg) |
02-5kokuyo-seki/DSC03150a_thumb.jpg)
大:隠岐島産
小:姫島産 |
02-5kokuyo-seki/DSC03151_thumb.jpg) |
|
| |
Ⅳ-(2)05後期・晩期の土器
05pottery/00DSC03143_thumb_1.jpg) |
05pottery/DSC03137_thumb.jpg) |
浅鉢形土器05pottery/DSC03138_thumb.jpg) |
05pottery/DSC03139_thumb.jpg)
十腰内遺跡(弘前市)
縄文晩期 大洞B-C式 |
05pottery/DSC03140_thumb.jpg) |
深鉢形土器05pottery/DSC03141_thumb.jpg)
亀ヶ岡遺跡(つがる市)
縄文時代晩期
大洞C2~A1式 |
注口土器05pottery/DSC03142_thumb.jpg)
十腰内遺跡(弘前市)
縄文晩期 大洞B-C式 |
|
|
|
|
|
|
| |
| |
Ⅳ-(3)
|
| |
| |
| |
Ⅴエピローグ
縄文の食料と米作り、そして弥生へ
|
縄文時代の食料にはドングリやその他の種子類があります。佃伊遺跡(淡路市)ではイチイガシ・オニグルミ・トチなどの木の実か゛発見されました。
特にイチイガシを貯蔵するための「貯蔵穴」が多数発見されました。また、薬にも なる「ゴボウ」、酒の材料になる「ニワトコ」など51種類もの種子が発見されました。
動物食料としては「シカ」「イノシシ」が多く、「イルカ」「クジラ」などの哺乳類の骨も出土しました。鳥類では「フクロウ」「ガン」「カモ」など、
魚類では「スズキ」「タイ」などがあります。縄文時代の自然豊かな様子が想像できます。 |
|
| Ⅴ-(1)縄文の食料と米作り、そして弥生へ |
Ⅴ-(1)01
01/DSC02917_thumb.jpg) |
縄文の食料と米作り、そして弥生へ01/DSC02918_thumb.jpg) |
01/DSC02919_thumb.jpg) |
壺(突帯文土器)01/DSC02920_thumb.jpg)
口酒井遺跡:伊丹市
縄文晩期 |
深鉢形土器
(突帯文土器)
01/DSC02921_thumb.jpg)
口酒井遺跡:伊丹市
縄文晩期 |
深鉢形土器
(波状口縁土器)01/DSC02922_thumb.jpg)
口酒井遺跡:伊丹市
縄文晩期 |
籾殻の拡大写真01/DSC02923_thumb.jpg) |
浅鉢(籾痕土器)01/DSC02924a_thumb.jpg) |
01/DSC02925_thumb.jpg)
口酒井遺跡:伊丹市
縄文晩期 |
01/DSC02926_thumb.jpg) |
浅鉢形土器01/DSC02927a_thumb.jpg)
口酒井遺跡:伊丹市
縄文晩期 |
石製包丁01/DSC02928_thumb.jpg)
口酒井遺跡:伊丹市
縄文晩期 |
|
Ⅴ-(1)02縄文の食料と米作り
|
口酒井遺跡(伊丹市)では縄文時代晩期の層から表面に稲の圧痕のある土器や、稲の穂摘み具である「石包丁」が出土するなど、稲の栽培を示す遺物が発見されました。しかし、水田跡は未確認です。九州や中国地方では縄文時代中期や後期の土器に籾の痕跡が確認されたことから、古くから稲を栽培していたと考えられます。
縄文時代には米作りをしていましたが県内では水田は見つかっていません。その後の灌漑用水路の整備や水田開発による「水田稲作」の開始を以て、弥生時代の始まりと考えています。
自然を糧としていた縄文時代から、食料確保のために土地を開発し、水田稲作をした弥生時代への変化を土器などでご覧ください。 |
02/DSC02929_thumb.jpg) |
縄文の食料と米作り02/DSC02930_thumb.jpg) |
縄文時代の食料加工02/DSC02930a_thumb.jpg) |
02/DSC02931_thumb.jpg) |
深鉢形土器
(突帯文土器)
02/DSC02932_thumb.jpg)
玉津田中遺跡:神戸市
縄文晩期 |
炭化米02/DSC02933_thumb.jpg) |
炭化米02/DSC02934_thumb.jpg)
玉津田中遺跡:神戸市
弥生前期 |
炭化米02/DSC02935_thumb.jpg)
玉津田中遺跡:神戸市
縄文晩期 |
深鉢形土器
(突帯文土器)02/DSC02936_thumb.jpg)
常全遺跡(太子町)晩期 |
深鉢形土器
(突帯文土器)02/DSC02937_thumb.jpg)
市之郷遺跡(姫路市)
縄文晩期 |
木製品(掘り棒)02/DSC02941_thumb.jpg)
玉津田中遺跡:神戸市
縄文晩期 |
02/DSC02942_thumb.jpg) |
|
| |
| |
Ⅴ-(2)弥生の水田稲作
|
今まで原野だった場所を切り開いて水田を造り、用水路を導入(掘削)して本格的な水田が整備されます。このような米作りの開始を以て「弥生時代の始まり」としています。県内各地で弥生時代前期の水田が発掘されています。 |
|
Ⅴ-(2)01
01/DSC02943_thumb.jpg) |
弥生の水田稲作01/DSC02944_thumb.jpg) |
01/DSC02944a_thumb.jpg)
米作りの始まり |
弥生土器
(壺・甕・鉢)01/DSC02945_thumb.jpg)
玉津田中遺跡:神戸市
弥生時代前期 |
01/DSC02947_thumb.jpg) |
01/DSC02948_thumb.jpg) |
01/DSC02949_thumb.jpg) |
01/DSC02950_thumb.jpg) |
01/DSC02951_thumb.jpg) |
|
|
|
|
Ⅴ-(2)02
02/DSC02952_thumb.jpg) |
02/DSC02953_thumb.jpg)
弥生前期の稲作水田跡
美乃利遺跡(加古川市) |
02/DSC02954_thumb.jpg) |
彩文土器
02/DSC02955_thumb.jpg)
丁・柳瀬遺跡(姫路市)
弥生前期 |
彩文土器
復元実測図02/DSC02956_thumb.jpg) |
02/DSC02958_thumb.jpg) |
02/DSC02959_thumb.jpg) |
02/DSC02960_thumb.jpg) |
木製品 (彩文鉢)02/DSC02961_thumb.jpg) |
02/DSC02962a_thumb.jpg)
丁・柳瀬遺跡(姫路市)
弥生前期 |
02/DSC02963_thumb.jpg) |
彩文鉢 復元図02/DSC02964_thumb.jpg) |
|
| |
| |
| Ⅵ年表・遺跡地図等 |
Ⅵ‐(1)兵庫県縄文時代主要遺跡分布図地名表
|
Ⅵ-(2)兵庫県縄文時代主要遺構年表
|
Ⅵ-(3)
|
Ⅵ-(4)縄文と出会う
|
| |
| |